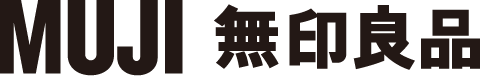捨てないくらし
佐久間 裕美子ライター
アメリカに暮らし、ニューヨークやポートランドで起きている新しいライフスタイルを追った『ヒップな生活革命』の著者・佐久間裕美子さん。消費社会とは距離を置き、信頼のおけるモノづくりの中に、作り手と買い手の新たな関係を見出す佐久間さんに、“捨てないくらし”について教えていただきました。
5年前、大雪が降って、ニューヨークの街のゴミ収集システムが数日間麻痺した時、自分が暮らすわずか8戸しかアパートのない低層ビルの前に積み上げられたゴミを見て、呆然としたことがあります。都会に暮らす現代人たちの暮らしは、大量なゴミを出しながら生活している。そしてそのゴミの決して少なくない分量が、土に帰ることもなく、リサイクルされることもなく、ゴミとして処理されていくのです。
その時から、私の生活に、「ゴミを減らす」という課題が加わりました。処分するゴミを減らすためには、自分が購入し、所有するモノの意味をひとつひとつ考える作業が必要になってきます。ショップで手に取るモノが、本当に自分にとって必要なものなのか、必要としている機能を果たしてくれるのか、壊れないものなのか、壊れた時、修復することができるのか、飽きのこないデザインなのか、信頼できる企業やブランドが作ったものなのか、これからの生活の中で愛し続けることができるのか、以前より深く考えるようになりました。
2008年に起きた世界を恐怖に陥れた空前の不景気の後、これまでの大量生産、大量消費のやり方に疑問を抱き、より丁寧に、より手を動かして、自分の手の届く範囲で、という新しいモノづくりの形、表現方法を追求する人たちに、ブルックリンやポートランドで出会い、2014年に「ヒップな生活革命」という本にまとめました。これがきっかけで、ヨーロッパや日本にも、似た価値観や問題意識を持ってモノを作ろうという作り手たちがいることを知りました。
こういう作り手たちが持つひとつの問題意識に、「これだけモノが溢れる時代に、モノを作り、売ることの意味」があります。たとえば、ブルックリンの<マーロウ・グッズ>はこれまで捨てられてきた食肉用の動物の皮を、時間と労力をかけて革になめすことで商品を作り、最近生まれたばかりの<フェタフォース>は、南半球で一番貧いと言われる国ハイチのアルティザンたちと協力して、ハンドメイドのバッグやキルトを作っています。
 もうすでに作られたテキスタイルや古いものを有効に活用していこうという考え方でやっている人たちもいます。ニューヨークの<アバシ・ローズボロー>は、一見フューチャリスティックなデザインのアパレル・ブランドですが、使っている素材は、デッドストックのテキスタイルばかりです。ブルックリンを拠点とする日本人デザイナーによる<トゥネス>は、ビンテージの衣類を縫製し直すことをコンセプトの軸に据えています。
もうすでに作られたテキスタイルや古いものを有効に活用していこうという考え方でやっている人たちもいます。ニューヨークの<アバシ・ローズボロー>は、一見フューチャリスティックなデザインのアパレル・ブランドですが、使っている素材は、デッドストックのテキスタイルばかりです。ブルックリンを拠点とする日本人デザイナーによる<トゥネス>は、ビンテージの衣類を縫製し直すことをコンセプトの軸に据えています。
 伝統工芸や昔ながらの手法との付き合い方を模索する作り手もいます。沖縄で訪ねた工房<木漆工とけし>は輪島で漆の技術を学んだ渡慶次夫妻は、故郷の気候に合った漆の器を、自分たちのスタイルに落とし込みながら、買う人が沖縄まで来てくれるような仕組みを考えている。東京のスウェット・ブランド<ループウィーラー>は、昔ながらの釣り編み機が消えていくのを救いたいという気持ちからスタートしたそうです。
伝統工芸や昔ながらの手法との付き合い方を模索する作り手もいます。沖縄で訪ねた工房<木漆工とけし>は輪島で漆の技術を学んだ渡慶次夫妻は、故郷の気候に合った漆の器を、自分たちのスタイルに落とし込みながら、買う人が沖縄まで来てくれるような仕組みを考えている。東京のスウェット・ブランド<ループウィーラー>は、昔ながらの釣り編み機が消えていくのを救いたいという気持ちからスタートしたそうです。
ものづくりの現場の人たちの、「こんな時代のモノづくり」への問題意識や表現方法を取材していくと、かわいい、欲しいという欲望だけでモノを買う行為がとても申し訳なく思えてきます。けれど逆に、どういう人たちが、どういう思いで、どういう生産背景で、どう素材を揃えてデザインに落とし込み、生産し、どうやって価格を決めているのか、そうしたことを知ることで、私たちの心をときめかせてくれるモノへの愛着はさらに高まっていくのです。
一度手に入れたモノを愛し、必要な時には修復したりしながら使う、それは大量消費、使い捨ての時代を経験したからこそ理解できるようになった考え方です。けれどそれは何もまったく新しい考え方ではありません。よくよく考えてみれば、おじいちゃんおばあちゃんの時代には、手を動かして作られた商品を、商店を営む人々と交流しながら購買し、修復しながら大切に使っていたのだと思います。
 2011年に亡くなった環境保護活動家でノーベル平和賞の受賞者ワンガリ・マータイさんは、多国語には訳すことのできない「もったいない」という概念を世界に広めるために尽力しました。私たち現代人の暮らしが環境に多大なる負担をかけていること、資源には限りがあることは、もう長いこと議論されてきましたが、「いつか破綻しますよ」というメッセージだけでは、贅沢な現代人たちの消費をやめさせる抑止力にならないこともまた厳しい現実なのかもしれません。だとしたら、作り手が目指すべきは、使い手が愛し続けることのできる機能性の高い商品、修復してでも長く使いたいと思わせる商品、捨てられない商品を提供すること、買い手にできることは、本当に必要なもの、愛せるものを見極めることなのかもしれません。
2011年に亡くなった環境保護活動家でノーベル平和賞の受賞者ワンガリ・マータイさんは、多国語には訳すことのできない「もったいない」という概念を世界に広めるために尽力しました。私たち現代人の暮らしが環境に多大なる負担をかけていること、資源には限りがあることは、もう長いこと議論されてきましたが、「いつか破綻しますよ」というメッセージだけでは、贅沢な現代人たちの消費をやめさせる抑止力にならないこともまた厳しい現実なのかもしれません。だとしたら、作り手が目指すべきは、使い手が愛し続けることのできる機能性の高い商品、修復してでも長く使いたいと思わせる商品、捨てられない商品を提供すること、買い手にできることは、本当に必要なもの、愛せるものを見極めることなのかもしれません。