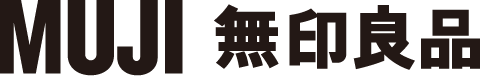眠りは、本能? それとも文化?
ここでは、霊長類研究者の座馬耕一郎さんと「ねむり展─眠れるものの文化誌」(以下ねむり展)の企画・デザインを担当された東南西北デザイン研究所の石川新一さん、そして、企画・共催のお一人でもある鍛治恵さんにふたたびお集まりいただきました。「人類に最も近縁な生き物」ともいわれるチンパンジーの眠りや、「ねむり展」で触れた眠りの多様性の視点から、われわれ霊長類ヒト科にとっての心地良い眠りを、いまいちど探ってみましょう。
座馬耕一郎

京都大学アフリカ地域研究資料センター研究員。1972年岐阜県生まれ。専門は人類学、霊長類学。現在の研究テーマは、野生チンパンジーの睡眠と夜間の行動。主な著書に『チンパンジーは365日ベッドを作る─眠りの人類進化論─』(ポプラ新書)など。
石川新一

東南西北デザイン研究所 デザイナー。1969年大阪府生まれ。GK京都を経て、東南西北デザイン研究所設立。現在,京都造形芸術大学非常勤講師,大阪工業大学非常勤講師。2014年SDA賞入選(INAXライブニュージアム 世界のタイル博物館)
鍛治 恵

1989年、ロフテー株式会社に入社。快眠スタジオに配属後、睡眠文化の調査研究業務に従事。睡眠文化研究所の設立にともない研究所に異動。2009年ロフテー株式会社を退社し、フリーで睡眠文化研究を企画する。2010年よりNPO睡眠文化研究会 事務局担当。主な共著に、「日本のねむり衣の歴史」(吉田集而編『ねむり衣の文化誌』冬青社)、「眠りの時間と寝る空間」(高田公理、堀忠雄、重田眞義編『睡眠文化を学ぶ人のために』世界思想社)。睡眠改善インストラクターとしての著書として「ぐっすり。」(新潮社)。

無印良品の京都の二店舗の店内で「眠り」の展示をしたのは2016年の春。実はこの時、市内の京都大学総合博物館で「ねむり展」が開催されていました。座馬さん、石川さんと鍛治さんが事務局を務めるNPO睡眠文化研究会は、この「ねむり展」実行員会のメンバー。これまで理系の知識で語られることが多かった「眠り」を、文化人類学、社会学、霊長類学なども含めた多様な学問の知見から紐解いた「ねむり展」は訪れた人々を固定概念からひきはがしてくれると話題に。(残念ながら会期は終了しています)今回は、さまざまな視点から眠りを考える3人に、眠りとは何かを、教えていただきました。
—座馬さんは、野生のチンパンジーの睡眠について研究をされています。野生のチンパンジーたちは少し変わった眠り方をするそうですね。
座馬野生のチンパンジーは365日、木の上に新しいベッドをつくって眠ります。数十本の枝を折り曲げて、長径約90cm、短径約70cmの楕円のベッドフレームをこしらえ、そこに弾力性のある小枝や葉をかぶせて。真ん中が少しへこんでいて縁の部分が少しもりあがっている、浅いお皿のような形のベッドです。ちなみにシングルです。作るのは木の上。低いものだと地上から5mくらい、高いものだと20mを超える高さにもなります。ビルの高さにすれば、2階から6階くらいでしょうか。
—そんな高い場所なんですね。座馬さんも眠ったことがあるとか。
座馬チンパンジーのベッドは本当に寝心地がいいんです。これまで寝たことのあるベッドの中で、一番気持ちのよいベッドだと断言できます(笑)。言葉ではなかなか表現できないのですが、固くもあり、やわらかくもあり。生の枝でできているので本当にしなやかで。さらにその上にふかふかとした葉っぱをしきつめているので、やさしい寝心地です。ベッドの中のくぼみがあるので包まれているような安定感もあり、寝相にあわせた心地良いゆれもあり、とにかく体に寄り添ってくるので、安心して体を預けて眠ることができます。チンパンジーの他に、ゴリラやオランウータンなどの大型類人猿もベッドを作りますが、他のサル、たとえばニホンザルはベッドを作りませんね。
—そんなに高性能なベッドを作れるのは、やはり知能が高いといわれる大型類人猿だからこそ、というわけですね。
座馬実はその逆という仮説があります。簡単にいうと「よく眠れたから知能が進化した」ということでしょう。知能の発達にはレム睡眠とノンレム睡眠のバランスが大切なのではないかと考えられているのですが、このうち、レム睡眠中には、どうしても、体幹の筋肉がゆるんで、だら~とした姿勢になります。木の枝で座って眠る他のサルたちは、なかなか筋肉をゆるめることができませんが、チンパンジーなどの大型類人猿は、敵のやってこない枝の先にこしらえた寝心地抜群なベッドで眠りにつくことができます。その結果、レム睡眠もノンレム睡眠もバランスよくとることができ、知能が進化したのではないかと考えられています。
—なるほど。眠りがチンパンジーを進化させたということですね。
石川人間も同じですよね。外山滋比古さんの『思考の整理学』という本に、簡単なことの例えとして「朝飯前」という言葉が用いられています。それって実は、目覚めてから朝ご飯を食べるまでの時間が、頭が冴えていてなんでも簡単にできてしまう、という意味なのではないかと思うんです。最近、自分のまわりにいる第一線で活躍する人たちが


「昼寝」に対して寛容になってきている気がします。それに彼ら、なんだか昔から寝ていた節も感じるんです。公表していなかっただけで。昼寝がよいことを自然と知っていたのかもしれません。そういえば同書に、三中(無我夢中、散歩中、入浴中)三上(トイレの上、馬の上、枕の上)にあるとき、いいアイディアが浮かぶ、といったことが書いてあり、すごく、眠りが脳の発達=進化に関係しているのではないかと思ったりします。
鍛治眠りと脳のパフォーマンスは、密接に関係しています。ところで、確かチンパンジーさんたちも、昼寝をするとか。
座馬昼寝のためにベッドをつくることもあれば、枝を電車のつり革のようにつかんで眠ることもあります。その姿はまさに通勤電車のサラリーマンそのものです(笑)。
石川研究者の中には、行き詰まったときこそ迷わず眠る、という強者も多いですよね。
鍛治上手にとれば、昼寝は活動の効率を上げるために効果的なもの。パワーナップという言葉もありますから、15分くらいの睡眠なら、ネガティブにとらえずにとっていただきたいです。
—鍛治さんは、『ぐっすり。』の中で「眠りはとても生理的な活動である一方で、どんな社会に暮らしているのかということに左右される」とおっしゃっていました。
鍛治眠りと社会を切り離して考えることはできません。今の日本では、まだ眠りを削るということに価値を置かれたり、あるいは寝ないで頑張ったということが、すごく評価されたりしていますよね。今、日本は、睡眠時間が短い国の世界ワースト3に入っているのですが、長い・短いの差は民族の生理の違いということではなくて、価値観とか社会のあり方の違いに影響された「文化の違い」ということだと思います。そういう意味では、今、あるいはこの先の人の眠りを考えるためには、睡眠の生理の仕組みを科学的に明らかにするだけでなく、社会学や人類学、霊長類学といった研究領域と、自然科学系の領域の知見が相互に対話しながら読み解いていく学際的なアプローチが必要なのではないかと思っています。今日の私たちの睡眠に関する知見は、近代以降の社会で進められた研究によるものです。それは、長い人類史の中のほんの短い時間といえるでしょう。人類に近縁な霊長類たちを研究する視点が入ることで、ヒトの眠りの進化について考えが深められるのではないかと睡眠文化研究会では考えています。
石川私はデザイナーという仕事柄、アイディアが結実するまでは帰らずに何日も徹夜して仕事をすることも珍しくありません。そんな「眠りの劣等生」の自分が、「ねむり展」の展示デザインを担当することになり、正直いいものかとはじめは後ろめたく思いました(笑)。でも「睡眠文化研究会」のメンバーでもある重田眞義先生(京都大学アフリカ地域研究資料センター長)が「それはそれでいい。そういう石川さんにこそ関わってほしい」といってくださり、とたんに気が楽に。先生いわく「眠りは本能に基づく行為だけれども、暮らしている社会によって変わるもの」。ちなみに私の眠りは狩猟民族の眠り方だそうです。獲物が獲れるまでは眠らない。獲れたときにがーっと眠る。それはそれで一つのスタイルだと。
鍛治「ねむり展」では、さまざまな寝具を使って世界の多様な眠りのかたちの一端を展示しました。
石川眠りは生まれ育った環境や文化、社会によって形作られています。枕ひとつとっても、眠りの形は本当にさまざまだということを示せました。例えばエチオピアの枕は、木でできていてとにかく固い。男性は、この木製の枕を自分で作るのだそうです。社会としての枕です。一方で、アジアの国々には涼しく眠れるよう籐で編まれた枕や陶枕等があります。これはきっと機能性重視。そして江戸時代に生まれて、女性の間では昭和に入るまで使われていた日本の箱枕には、眠りに必要な道具が入れられる引き出しがついていて。コンパクトに収納して持ち運び、旅先で枕として使っていました。日本人はきっと昔からそういうことを楽しんでいたんでしょうね。
座馬枕に関してはチンパンジーのベッドにもあります。あるどころか、頭の枕だけではなく、足枕、抱き枕までついていますよ。楕円の縁がふっくらとした枕になっているようなイメージです。チンパンジーは寝相によってこの枕を使い分けています。実際チンパンジーのベッドは本当によくできていて、知れば知るほど「なるほど」と思う部分が多いのです。
—とても気持ちがよさそうです。むしろ人間の平らなベッドより寝心地がよさそうに見えますね…
座馬人間の平らなベッドと、チンパンジーのお皿のようなベッド。一見、全くちがうように見えるのですが似ているところもあるんですよ。むしろ、人間のベッドって、平らのように見えますが、枕とか使いますので、どちらかというと、枕という「どこか盛り上がった部分のある」ベッドで寝ているという方がいいかもしれません。抱き枕や足枕も使って寝ているならば、チンパンジーのベッドとの共通点の方が多いくらいです。
—自然環境にいるチンパンジーの眠りは我々ヒトの「祖先の眠り」と大変近くにあるように思います。人間とチンパンジーの眠り方はやはり似ているのでしょうか?
座馬似ていると思います。チンパンジーはいつも同じベッドを作るのではなくて、何十本もの枝を使ってベッドを仕上げる日もあれば、10本ほどの枝でささっと寝支度をととのえて寝てしまうこともあります。もしかしたら、疲れている日には簡単なベッドでバタン、キューと寝てしまうのかもしれません。時間をかけて入念にベッドを作る日は、一回寝転んだあとで、また起き上がり、葉っぱのついた小枝を一本重ねたりして、何度も寝心地を調整することもあります。その様子を見ていると私たち人間にも、ただ眠るのではなく「気持ちよく眠る」ということに対する欲求がもともと備わっているように思えてきます。
鍛治人間もチンパンジーも、昼間の時間をどう過ごしたかが眠りに影響する眠りのメカニズムは似ているようですね。
座馬それに、実は野生のチンパンジーの眠りは本当に柔軟で。何しろ毎日ちがうベッドをつくっていますから。一日一日、眠る時間もちがいます。睡眠欲求を素直に受け入れていますね。朝までぐっすり眠っている日もあれば、夜中に起きて数時間、なにやらごそごそしてから眠る、なんてこともよくあります。以前、あるチンパンジーがベッドから起きてこないことがありました。やっと起きたと思ったら二度寝。心配になって待っていたら、なんと結局お昼前までうだうだとしていて。
鍛治ひょっとしたら前の日たくさん歩いたのか、ごはんを食べ過ぎたのかも。
—チンパンジーも寝坊するんですね。少しほっとします。
鍛治人間も、眠れなければ無理して寝なくてもいいんですよ。真面目な人ほど「眠らなくては」というプレッシャーで逆に眠れなくなってしまうようですが、部屋を片付けたり、本を読んだり。すきなことをしてまた眠くなるのを気長に待ちましょう。
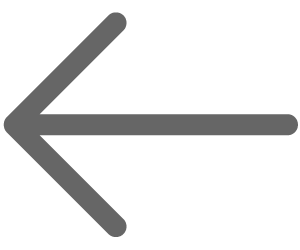 眠りは、はじまり
眠りは、はじまり