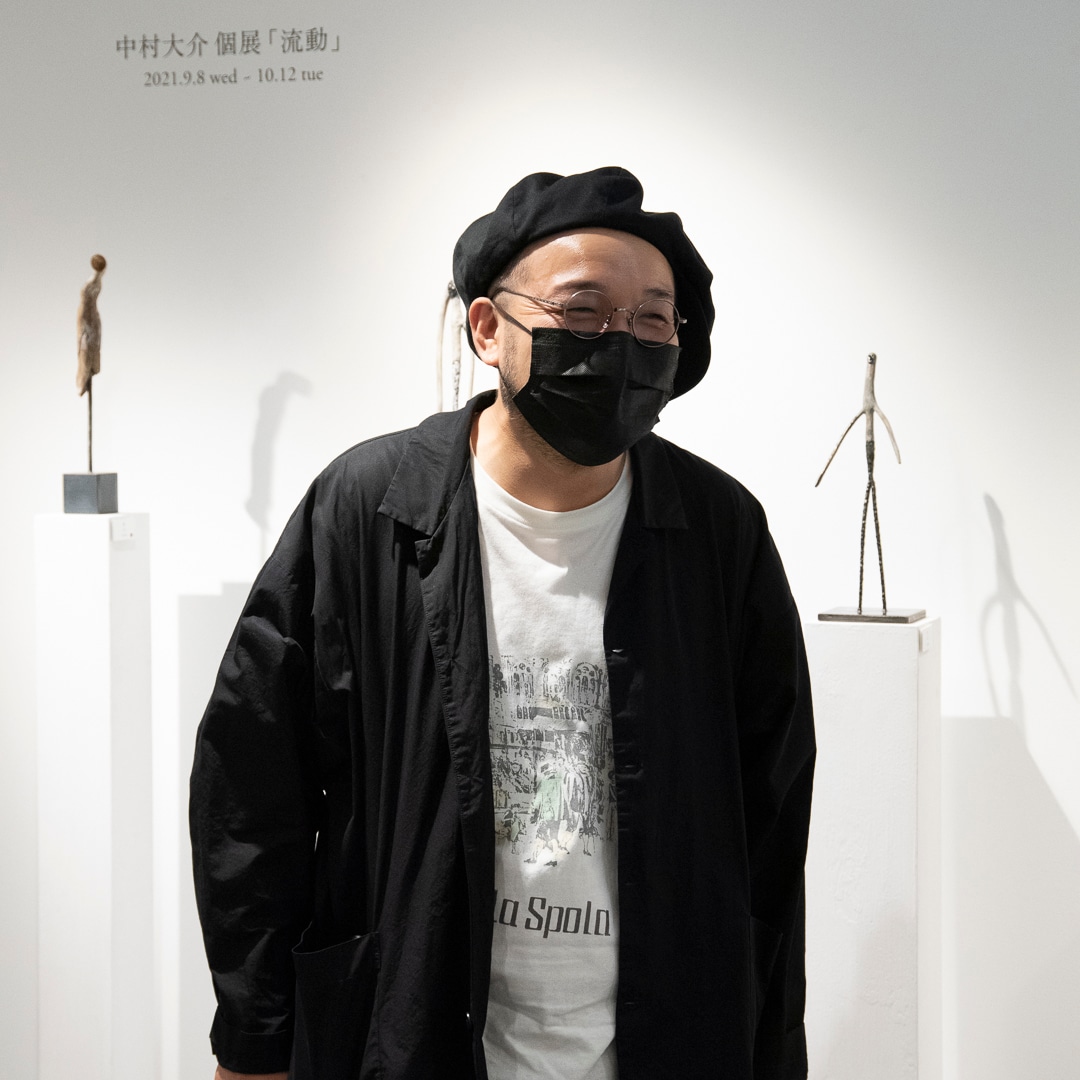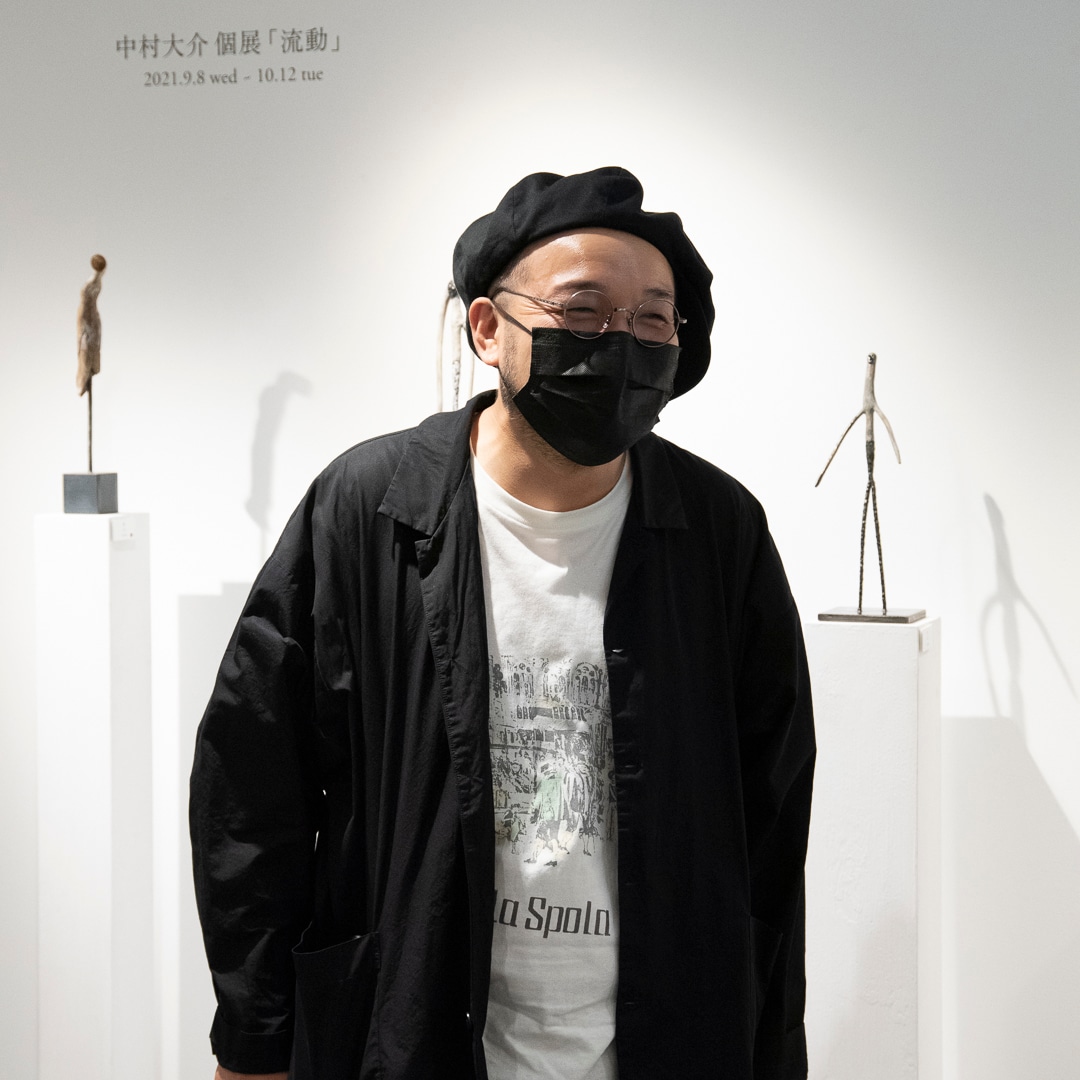IDÉE TOKYOでは9月8日(水)より彫刻家・中村大介氏の個展を開催しています。
これに際して中村さんに作家として活動するようになったいきさつやインスピレーションの源泉、そして今展に向けた思いを伺いました。
記事は前編・後編の全2回です。
○後編
―はじめに、作家活動を始めるようになったきっかけを教えていただけますか。
彫刻をやる前は鉄で小さな人形を作り、童話世界の作品を制作していました。山に登り始めてから山の植物や動物達からインスピレーションを受け、山の神様を制作するようになりました。
―現在のように作品発表をされるようになる前、ICSカレッジオブアーツ(東京都目黒区にある建築・インテリア・家具の専門学校)に入学されていましたね。
山登りをしていなかった20代の頃は音楽が好きでした。高校生のときにラップやっていたんですけど、19歳の頃にラップをこのままやり続けるか考えていたんですが、元々インテリアにも興味があって。東京に来ていた友達が紹介してくれたのが、ICSカレッジオブアーツでした。
ICSには家具を作れるようになりたくて入りました。授業では木材を使って制作するんですが、自分は金属で作りたかったんです。どうしたらできるのかを調べていたときに、知り合いから金属を扱って制作している工房を教えてもらって働いていたんですが、そこにたまたま小林(モリソン小林氏:5月にイデー東京でも個展を開催。詳細はこちら)がいたんですよ。
僕が工房でアルバイトとして働くようになって1年くらいで小林は独立して、いまあるスペシャルソースのシェアアトリエで活動していました。そこは椅子張り屋さんとか木工をやっている方もいた場所だったんですよ。僕もICSを卒業してから手伝いに行っていたんです。
それから椅子張り屋さん、木工制作をしている方もシェアアトリエから独立して別な場所に移り、スペシャルソースだけが残りました。2013年以前は山びこを作っていなくて、什器や家具製作がメインで。椅子張り職人さんが使っていた2階を改装してギャラリーにしてからは制作と展示の場所になりました。
この頃にアルバイトで木工やっている子が来てくれていたんですが、その子の影響で山登りをするようになりました。8年くらい前ですね。初めて登ったのは山梨の山でした。名前は出てこないんですけど(笑)。高山ではなかったですね、日帰りで低山を登りました。
―今展の作品についてもお話しを伺いたいです。アイヌ語やギリシャ神話に基づく名前を作品につけてらっしゃいますね。中村さんはもともとそうしたことがお好きなのかなと思いました。
例えば今回の作品にもある古名もそうなんですけど、普段生活しているとそういう情報って入ってこないじゃないですか。ひらがなだと日本のものってわかるけど、カタカナにするとどこの国かわからない。言葉の響きだけでどんな意味があるのかを想像するのも面白いなと思っています。古い名前がどういう意味なのかわからなくても、調べることでそのものの起源を知ることができます。だからなるべく既にあるものの名前ではなく、いろんなところから選んで作品名をつけるというのを昔からやっています。
(中村さんの作品のひとつ、ユークはアイヌ語でエゾシカの意味を持つ言葉。二本の白く美しい角も木でできており、垂直方向に向けてつくられた形は、さながら人間と出会ってこちらを窺うかのように立ち上がった姿とも見える。現在も北海道全土に生息しているエゾシカは古来アイヌ文化と関わりの深い動物であった。)
(作品チウチリはアイヌ語でセキレイの意。小柄な美しいセキレイも北海道日高地方に伝わるアイヌ神話に登場する。神が世界を創造することを決意したとき、自らの助手としてセキレイを地上におろした。セキレイは神がツルハシと斧で開墾した土地を爪でかき、翼で打ち、尾を上下して叩いて固めた。今もセキレイが尾を上下させているのはこの働きをしたためだという。)
――「移り変わっていくことを愉しんでいきたい」と主旨文に書かれていますが、物事の移り変わりを山へ行くたびに感じてられてきたのかなと思います。
もちろんそれもありますね。花なども、去年咲いていた場所に今年は咲いていない。また逆も然りで、全部そろって毎年同じものを観れることはほぼないと思う。そういう自然、動物、人の姿かたちというのも変わっていくし、ずっと同じ感情というのもない。ちょっとずついろんなことで変わっていく。今回はそういう意味も含めてパンタレイ(panta rhei :古代ギリシアの哲学者へラクレイトスの思想をあらわす語で、すべてのものは流れ、何ものも絶えず変化していくという意味がある)というタイトルにしました。
(撮影地:白馬岳)
あとは自分のなかでもこれまでと違う作品、新しいものを出したいという気持ちがありました。「今回の展示は鉄がメインの作品も作ろう」と思って始めた時期の作品がアメツチです。
(丸い鉄材同士を溶接して作られたアメツチは天の神と地の神。頭から胴体にかけては大木のようでもあり、隆々とした根には古木のたくましい生命力を感じられる。半円をつなげたような顔は陰と陽、月と太陽を表しており、まさに天と地を繋ぐ大いなる神といえる。)
木と金属を使って制作してきたので、いくつかできることがあるんだったらそれを混ぜてやってもいいんじゃないかなって思ったんです。土台に鉄を使うのはよくやっていたけど、土台に限らず作品のメインやメインの一部に鉄が入るものいいんじゃないかと。
-制作の際には、はじめにデッサンをしたりしてイメージを固めているのでしょうか?
木を使って作るときは、目の前にある木を見ながら作っていくので普段はしません。作品は自分のイメージに合わせていくというよりも、元々の木の形に合わせて作っています。ただ鉄作品に関してはイメージからデッサンを描いても思ったように作れない試行錯誤があったので時間がかかりました。
<後編へつづく>
今回インタビューに応じていただいた中村さんの個展は10月12日(火)20時まで開催しています。IDEE TOKYO公式インスタグラムアカウント、
IDÉE SHOP Onlineでも展示作品をご紹介していますので、併せてご覧ください。
また、今展では作品のほかに「山びこ」の図鑑もご購入いただけます。編集・執筆を中村大介さん、写真はモリソン小林さん、版画を高里千世さんが担当した本書に中村さんが制作してこられた山に棲む神々「山びこ」たちの作品が納められています。店頭と通販の両方でご購入いただけます。
●山びこ図鑑 ¥4,500(税込)
〇期間 2021年9月8日(水)~10月12日(火)
〇場所 IDÉE TOKYO(クリックするとMAPが開きます)
JR東日本東京駅グランスタ地下北口改札を目指してお越しください。
お電話でも場所のご案内をいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。
TEL 03-5224-8861
〇instagram
IDÉE TOKYO公式インスタグラムアカウント
@ideetokyo
中村大介さんのアトリエ・スペシャルソース
@specialsource_atelier
中村大介さんアカウント
@d_nakamura
IDÉE TOKYO