あとからくるひとのために
「速いこと、最短コースは正しいこと? 目の前の誰かに歩数を合わせる」

2026/01/17
(イラスト・三好愛 取材と文・綿貫あかね)
おがわ・きみよ 1972年、和歌山生まれ。上智大学外国語学部教授。ケンブリッジ大学政治社会学部卒業。グラスゴー大学博士課程修了(Ph.D)。主な著書に『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)、『世界文学をケアで読み解く』(朝日新聞出版)、『ゴシックと身体』(松柏社)、『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』(岩波新書)など。近著は『ゆっくり歩く』(医学書院)。
スピードを緩めて、目の前の他者と歩調を合わせる。
——『ゆっくり歩く』っていいタイトルですね。難病を患っているお母さんの介護について書かれた本ですが、お母さんと歩くスピードが違うと気づいたのはどのようなきっかけだったのでしょうか。
小川公代さん(以下、小川):わたしは地元が和歌山なので、実家もそこにありました。父の死後、母はひとりで住んでいたのですが、体に異常を感じて関西で検査を受けたらしいんです。もしかするとパーキンソン病かもしれないというので、東京の病院でさらに検査を受けることになり、わたしが付き添いました。複数の検査を受けるため院内の廊下を歩いていて、母の歩き方がとてもゆっくりになっていることを、そのとき初めて意識しました。母はそれまで地元で趣味に打ち込んだり、調停委員の仕事をしたりと忙しく動いていたのに。「なぜこんなに歩くのが遅いんだろう」とショックを受けて。それと同時に、自分がこれまで誰かに合わせてゆっくり歩くという体験をしていなかったことにも気づいて、びっくりしたんですね。

今回のインタビューのベースとなった小川さんの最新著作『ゆっくり歩く』(医学書院)。高校2年にイギリス留学、そしてケンブリッジ大学に合格、帰国後は大学教授に。“直立人”の階段をまっすぐ駆け上がってきた娘は、病を得た母と一緒にゆっくり歩かざるを得なくなる。そのときどんな光景が目に入り、どんな声が聞こえてきたか、7年間の(そしてそれは今も続いている)の軌跡を綴ったエッセイ集。
——お母さんはそれまで活動的だったんですね。
小川:母とわたしとはちょうど30歳差です。5歳だったときに、母は35歳。それで、わたしが小さいときは歩くペースが逆だったことを思い出すんですよね。母がわたしの前をスタスタ、スタスタ歩いていた頃を。朧げに覚えているのは、先に歩いていた母の背中を追いかけていたこととか、その母がちゃんと待っていてくれて、追いついたときにつないでくれた手の温かさとか。そのときなぜか、よちよち歩きの子どもだった自分と、母との立場が入れ替わっていることを、なかなか受け入れられなくて。
——小川さんはもともと歩くのは速いほうなんですか?
小川:ええ。そもそもせっかちな性格なんですよ。だから、ひどい話ですが、病院の廊下でも、薬局でも、検査当時75歳だった母と歩いていることを忘れて、自分のペースでさっさと先へ進んでしまい、ハッと振り返ったら、母がすごく後ろを歩いている。気づいて戻っての繰り返し。
——何事も他者のペースに合わせるのは、最初はなかなか難しいですよね。
小川:『ゆっくり歩く』を書きながら考えていたのは、常にスピードのことでした。ゆっくりできない自分のこの性格は、生まれ持ったものなのか、習慣がへばりついて剥がれないせいなのか、とか。どうしたらゆったりできるのかという大きな命題を、いまも突きつけられています。だから母といるときは、焦らない、苛立たない、怒らない、この三つを心に留めています。でも、どうすればこの三つを制覇できるのかと考えてしまって。もう「制覇」という言葉を使っている時点で、ケアと正反対の思考癖、合理性が頭の中に固着してしまっていますよね。こんなにもケアを論じてきたのに。
——乗り越えるとか、成長とか、そういう思考でしょうか。
小川:わたしの生きてきたナラティブが、チャールズ・ディケンズやシャーロット・ブロンテとかの教養小説なんですよ。何かがうまくできるようになるには鍛錬や勉強が必要、というような。だからこの成長物語然としたナラティブに追い立てられて、挑戦の壁を乗り越え、課題を制覇しなければならないと思い込まされてきたんですよね。
——そういえば、小川さんは本を読むのもとてつもなく速い。
小川:イギリスで学んでいたときは、英語が速く話せるようになるとか、相手の話すスピードについていくとか、成功するためにはすべてを速くこなすことが絶対的な条件でした。ケンブリッジ大学では、日本人が読めるようなスピードではない冊数を毎日読まなければいけなかったから、速く読めるようになったんです。母国語ではない言葉で週に何十冊も読んで、毎週論文を書くというとんでもないスパルタ地獄。これまでは『ゆっくり歩く』とは正反対の人生を求められ続けてきたんですよね。そのまま没頭して、気づいたらいろいろなスキルがつきましたけれど。
——効率よく速く処理するなど、常にスピード勝負の人生。それがお母さんの介護をしてきた約7年の間に、どのように変わっていったのでしょうか。
小川:スピードを出すことばかり考えていたのに、介護が始まったらその速さはまったく活かせないんですよ。無駄に処理速度が速い自分がうらめしい。せっかくこんなにいろいろなことが、ハイスペックにできるのに、病気の母に対しては何の役にも立たない。あえて役に立ったことといえば、電車に乗ったときに母を座らせるための空席を、いち早く見つけられるようになったことですね。優先席が満席でも、ちょっと顔を上げて立ってくれそうな優しい人がいると、「お母さーん、替わってくださる、かもよ?」と大きめの声で話して、まだ立っていないのにお礼を言うとか。本当に申し訳ない話なんですが、つらそうに立っている母を見ていられなくて……。
——これからの多様性やコミュニケーションがさらに重要視される社会では、目の前の相手のペースに合わせていくことも求められますよね。小川さん自身も変化の途中、ということでしょうか。
小川:そうですね。まだまだできないことがたくさんあります。パーキンソン病は脳の病気です。だから思考の処理も遅くて、考えるのに健常者の3倍も4倍も時間がかかる。言葉も出てきにくい。それをわたしもわかっているのに、早く答えてほしいと思ってしまう。その症状は脳の処理が遅れているだけで、少し時間をおけばちゃんと脳に沈澱するんです。でも母のその状態をどこかで認めたくない自分がいて、待てずに「もうお母さん、しっかりしてよ」と怒ってしまう。だから、わたし自身もこれまで刷り込まれてきたものが、簡単に剥がれないことを痛感せざるを得ません。
——スピードを緩めてお母さんに合わせられる、何かいい方法を編み出せましたか?
小川:脳が早く処理できないという事実を受け入れて、それをどうケアするかという考え方を取り込めるように日々格闘しています。母がそういうことに直面するたびに「脳の処理スピードの問題だから」と、いったん自分に言い聞かせて飲み込む。そしてひと呼吸置いてから「こうなの?」と解釈してあげる。ゆっくりしか考えられない母と「食パンはないけど、ピーナッツバターパンがおいしそうよ」とか、アイデアを共有すると、できない苦しさも楽しいことに変わる場合もある。ゆっくり考えている時間を使って、新たなクリエイティブなアイデアを一緒に生み出す、という方向にシフトしていけるようにしています。わたしはようやくそれが少しずつできるようになってきたところです。
困っている人から伸びてくる、ツタ力(りょく)のワザを広めたい。
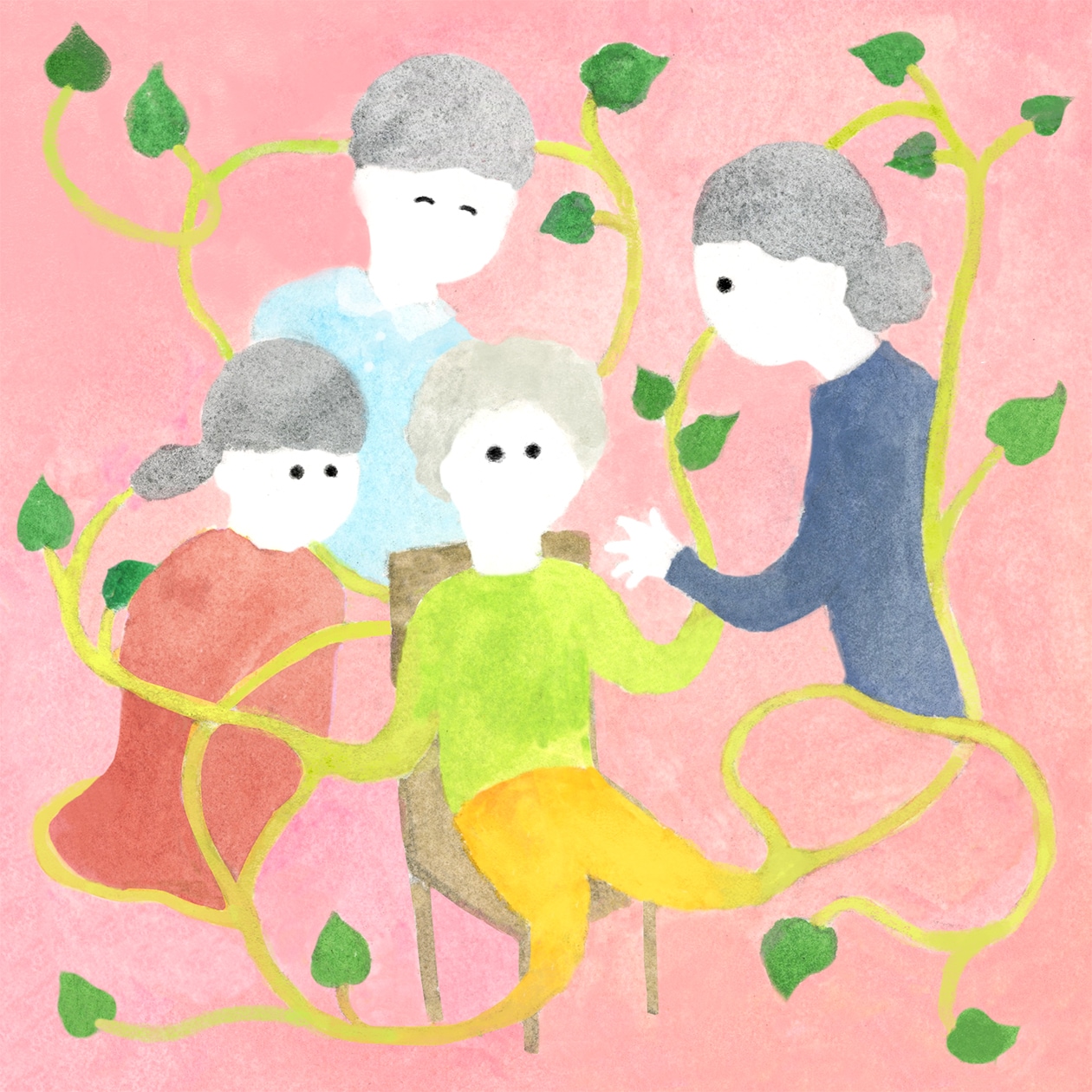
——お母さんはいま、小川さんの自宅近くの介護サービス付きマンションにお住まいとのこと。生活のサポートもある程度必要な状況でしょうか。
小川:母が歳を重ねるにつれ、自分でできないことが少しずつ増えてきています。手が震える症状があるので料理はできない。でも3食すべて介護サービスで用意されるわけではありません。わたしが料理をしに行ったり家に来てもらったりして補完していましたが、すべてを網羅するのは無理です。それで、後で知ったのですが、なんと母は友達を作って、ミルクとかヨーグルトとかちょっとしたものを、ついでに買ってきてもらうというワザを編み出したんですよ。それ以前は「こんな体で人前に出たくない」と言っていたのに。もちろんその人と仲良くなりたいという気持ちはあると思うのですが、サポートが行き届かず困り果てた末に、努力して友達を作ったんですね。それを聞いて感動してしまって。
——お母さんは人に頼ることを、あまり躊躇しない性格なのでしょうか。
小川:もともと自分に困りごとがあったら、周囲に自然と頼る人ではありました。他者に軽やかにくるくるっと巻きついて、自分の希望を実現させる。その力を、かつて母が占い師さんに『蔦』のようだと言われたのを聞いていたので、“ツタ力(りょく)”と名づけてみました。ただ、元気だったときのツタ力と、難病になってからのそれは少し質が違っていて、いまはこちらが拒否できない段階まで、ある程度自分で進めてからこっちにやってくるんですよ。「調べたらここにあるらしいから、ちょっと問い合わせてみてくれない?」って、ふわっと頼まれると、「じゃあ、やってあげようかな」と。やる気にさせるツタ力に進化しています。
——いいですね、ツタ力。自分の面倒は自分で見ろ、他人に迷惑をかけるな、という自己責任論が強まる世の中を、弱者の立場から覆していく小さな作戦のようです。
小川:ツタ力はガンガン応用してほしいですね。そもそもコミュニケーション能力の高い人だけが、ものを頼めるというのはおかしいと思います。コミュニケーション能力には多種類あって、言葉巧みにプレゼンテーションができる人の商品が売れない場合も、逆に口がまったく立たないけれど困っているから助けてもらえる場合もあるものだから。
——そうやって困っていたら周りが自然と手を差し伸べてくれるというのは、津村記久子さんの長編小説『水車小屋のネネ』(毎日新聞出版)みたいですね。頼るほうも頼られるほうも、程よい距離感でコミュニケーションを取る。あとからくるひとへの希望につながります。
小川::『水車小屋のネネ』は『ゆっくり歩く』でも触れましたが、母が備えているツタ力は確かにそれによく似ています。ぜひ新しい価値として広まってほしいですね。強者だけが得をして弱者を苦しめるような、いまの行き過ぎた資本主義社会は容易には覆せない。でも他方で、弱い人がいたら助けるという人間の本能も信じていきたい。それが本来の人間の姿だと思えるような、そういう価値がケアなんだとわたしは思っていて。あとからくるひとのためにも、そういう社会に少しずつでも戻っていくといいですよね。

「MY FIRST MUJI〜無印で揃えたかった念願のアイテム〜」
「30歳で東京に住み始めたとき、上智大学の嘱託雇用で、学生の前で講義をするため、ある程度きちんと見える服が必要でした。ただ、まだあまりお金がなかったこともあり、無印良品にはお世話になりました。その頃の金銭感覚では、それでも高いと感じていたことや、思い出もあって、いまでもなかなか捨てられません。それから正規雇用となって、昔の自分からは考えられないような買い方をしたのが本棚です。自宅を仕事場の近くに移したのを契機に、どちらの本棚も無印良品で調達しました。本棚は商売道具。いつかは無印良品で揃えたいと思っていたんです。自宅の本棚を眺めながら、かつての自分を思い返すと、成長したなぁと感慨深いです」
← 前の記事へ
← 前の記事へ




